ミヤコヒキガエルの餌付けに成功した方法とおすすめの餌を紹介!!


本記事は
お迎えしたミヤコヒキガエルの餌付けは思いの外大変だった!!
というお話です。
ミヤコヒキガエルのがまくんと、かえるくんをお迎えして6ヶ月が経とうとしている。
2匹とも、もっちり、むっちりしたヒキガエルらしい姿をしている(特にかえるくん)。
▼ミヤコヒキガエルの飼育方法についてまとめた記事はこちら
お迎え当初は、2匹とも5センチ程度。
がまくんはかえるくんより明らかにひと回りくらい小さいかった。
それは現在でも変わらない。
今でこそ、ほぼ何でも食べてくれるがまくんとかえるくんだが、お迎え当初は給餌に相当苦労した。
お迎え当初はまだ環境に慣れていない影響もあって、給餌しようと扉を開けただけでがまくんとかえるくんは大騒ぎ。
ミヤコヒキガエルはあまりジャンプしないと聞いていたがジャンプしまくりである。
そんな、がまくんとかえるくんに、色々と試してみた方法を紹介していきたい。
フタホシコオロギをピンセットで給餌
まずは給餌の王道。
ピンセット給餌。
餌はフタホシコオロギのsサイズ(1センチ未満)。
かえるくんに関しては餌とわかればすぐに近づいてきた。
ピンセットからもあっさりとコオロギを食べた。
試しに人工餌(ヒカルベルツノ)を小さくちぎってピンセットでつまんでかえるくんの目の前で動かしてみた。
あっさりと食べるかえるくん。
慣れるまでは活餌を覚悟していたので少々驚いた。
まあこれは嬉しい誤算。
ピンセット以外の方法で、餌も色々と試してみたが、かえるくんは基本何でもOKのようだった。
食い意地がはっているのだ。
一方で苦労したのはがまくん。
もちろんピンセットからは食べてくれない。
とにかくピンセットでつまんだ餌には興味をもたない。
おそらくピンセットを怖がっているのだろう。
餌を顔の前に近付けても下を向いてしまう始末。
あまりしつこいと小便を漏らしながら逃げてしまう。
人工餌など論外だ。
怖がって下を向いてしまうがまくんは、なんだかちょっと可愛く思えたが、あまり悠長なことも言っていられない。
餌を食べないと大きくならないし、まだ大人ではないので生死にかかわってくる。
強制給餌はできるだけ避けたかったので、色々と試行錯誤を続けた。
コオロギを水入れで泳がす
とにかく我が家のミヤコヒキガエルたちはびびりなのだ。
ちょっと覗き込んだだけで小便をチビリ倒して大騒ぎ。
しかしかえるくんはすぐに食い意地に負けてしまう。
餌らしい気配があると近付いてくる。
ある時、たまたまかえるくんに与えようとしたコオロギが水入れに落下。
そのままだとコオロギが溺死してしまうので水入れの中でもがくコオロギを急いで救出しようとしたところ。。。。
水入れの中にいたがまくんが、水入れでもがくコオロギに興味をもった。
パチンっ!!
偶発的とはいえ、これががまくんの初給餌となる。
がまくんの給餌に一筋の光が見えたように感じたがそうでもなかった。
コオロギの泳がせ具合が非常に難しいのだ。
着水させたコオロギを、がまくんの目の前を通過させて、コオロギが息絶える前にがまくんに認識してもらわなければならない。
コオロギのサイズも難しい。
与えたコオロギはフタホシコオロギの1センチ未満のサイズ。
これよりコオロギのサイズが大きいと、がまくんは怖がって逃げるのだ。
溺れて溺死寸前のコオロギを怖がるなんてびびりにも程がある。
うまくいけば食べてくれるが、がまくんが満腹になる前に大量のコオロギの溺死体ができあがる。
溺死体は、毎回ツノガエルたちが処理してくれていたが、非常に非効率・非経済的だった。
人工餌をテグスで給餌
次に試したのは、テグスと人工餌を使った給餌。
テグスの先にヒカリベルツノを小さくちぎってつける。
テグスの端を持って、がまくんの目の前でゆらゆら。
これは結構食べてくれた。
手が近かったりすると警戒するので、もしこの方法を試すのであれば、テグスは少し長めに切って使用することをおすすめする。
テグスが短すぎると、テグスを持つ人間の手を気にして逃げてしまったり、怯えて食べなかったりするからだ。
床材にペットシーツやキッチンペーパーなどを使っている場合は、テグスを引いて床材の上で人工餌を動かしても食べてくれる。
ただしこの方法は相当面倒くさい。
まずは、餌が大きすぎると怖がるので、テグスに付ける餌の大きさは5ミリ程度。
更に絶妙な硬さにふやかさないとすぐにテグスから外れてしまう。
一度やってみるとわかるが、この作業はかなりイライラする。
そしてもう一つの問題が発生。
カエルくんによる餌横取り問題。
がまくんのために苦労して準備した人工餌。
がまくんの目の前でブラブラさせていると、それをみつけたかえるくんがあっという間に横からきて食べてしまう。
かえるくんの食い意地は底なしで、先にかえるくんの給餌を済ませていても、餌とわかればすぐに横取りをしにくるのだ。
この横取り問題は、他の方法を試す上でも大きな問題となってくるので、かえるくんには、がまくんの給餌の間は別のケージ(マルチケースM)に入っていてもらうことに。
ちなみに妻は、このマルチケースのことを独房と呼ぶ。
このテグスを使用した給餌は、それなりに食べてくれたので成功といえば成功。
しかし、とにかく手間がかかる。
あくまで選択肢の一つといったところか。
▼丸めやすく形も自由自在!!おすすめの人工餌はこちら!!
→レオパやカエルに練り餌タイプの人工餌(レオバイト)のススメ
透明スプーンで給餌
人工餌でも、目の前で動かせば食べてくれることがわかったので、引き続き人工餌を使っての給餌にトライした。
なんとかがまくんが怖がらない方法で、目の前で人工餌を動かさなければならない。
色々な情報から利用してみたのが、コンビニやスーパーなどでカップヨーグルトやカップアイスを買った時につけてくれる透明のプラスチックスプーン。
結果として、このスプーンは大成功だった。
柔らかくした人工餌を必要な大きさにちぎってスプーンに乗せてがまくんの目の前でゆらゆら。
ハッとした感じで餌に気づいたがまくんをしばらく様子をみた後、パチンッ!!
なんともあっけない。
おそらく透明なスプーンはほとんど見えていないため、怖くないのだろう。
ここでもやはり、餌を大きくしすぎると食べなかった。
コツはスプーンはゆっくりと近づけることと、目線よりも低い位置スプーンを動かすこと。
調子に乗って急いで動かしたりするとやっぱり小便をちびりながら逃げてしまう。
しかし、この方法は人工餌に慣らしたい場合にもかなり有効な方法ではないだろうか。
とりあえず、がまくんを餓死させてしまう心配はなくなった。
ワラジムシ・ミルワームの置き餌
スプーンでの給餌以外に有効だったのが、ワラジムシ・ミルワームの置き餌。
特にワラジムシはかなり好物なようだ。
1センチを超えない程度のワラジムシを、側面がツルツルした餌入れに入れてケージの中に置く。
餌入れをケージに入れるだけでびびりまくりのがまくんは大騒ぎ。
すぐに隠れてしまう。
気にせずせのまま餌入れをケージに置いておく。
しばらくしてケージを確認すると、餌入れのそばでジーッと餌入れを覗くがまくん。
更にそのまま10分くらい放置しておくと、餌入れの中のワラジムシは空っぽ。
少し大きめのワラジムシを混ぜておくと、きれいに大きめのワラジムシだけ残す。
少し身体が成長するまでは、大きめの餌を怖がる状況は続く模様。
しかしこの方法はかなり楽だ。
自宅周辺には公園も多く、ワラジムシの入手には困らない。
▼飼育も簡単!!ワラジムシの飼育についてまとめた記事はこちら
給餌にたいして手間もかからず、カルシウムも豊富。
実際のところ、がまくんは、お迎えから2ヶ月くらいまでは、餌はほとんどワラジムシだ。
ミルワームでも置き餌を試してみたが、小さめのミルワームであれば問題なく食べてくれた。
ちなみにこの時もがまくんが食べ終わるまでカエルくんは独房へ。
横取り番長のかえるくんが居たら、小さなワラジムシたちはあっという間にお腹の中に入れられてしまう。
コオロギの撒き餌も考えが、小さめのコオロギは、すぐに床材の赤玉土に潜ってしまう。
コオロギの糞尿で床材を汚されるのがオチだろう。
まだ体が小さいだけに、赤玉土の誤飲も心配だった。
▼赤玉土1択!?ミヤコヒキガエルの床材についてまとめた記事はこちら
→レイアウトも映える!!かわいいミヤコヒキガエル飼育の床材は赤玉土で決まり!!
コオロギを与えたいのであれば、溺死覚悟で水入れの中を泳がすか、後ろ脚を抜いて餌入れに入れて置き餌をするかのどちらかだろう。
ただしSS〜Sサイズのコオロギの脚を抜く作業が苦にならない方にはいいかもしれない。
まとめ

何故かこのように同じ方向を向いていることが多いがまくんとかえるくん
透明スプーンとワラジムシの力を借りてなんとかひと回り以上は成長できたであろうがまくん。
お迎えから6ヶ月たった現在、相変わらず2匹ともびびりの小便たれであるが、給餌に苦労することは一切ない。
成長したがまくんは、まだまだ小さく頼りない感じもするが、かえるくんに引けをとらないくらいの食い意地を見せつけてくる。
Sサイズのコオロギにびびっていた時が嘘のように、多少大きめのワラジムシやコオロギにも果敢にアタックしてくる。
人工餌もモリモリ食べる。
当初、餌の横取り番長はカエルくんだったが、今では横取りの応酬である。
独房と呼んでいるマルチケースも最近はめっきり出番がない。
これから初めて寒い冬を迎えることになるが果たしてこの食欲は続くのだろうか。
最後まで読んでいただきありがとうございました。








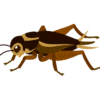







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません