ミヤコヒキガエルの餌に!再びワラジムシの飼育繁殖
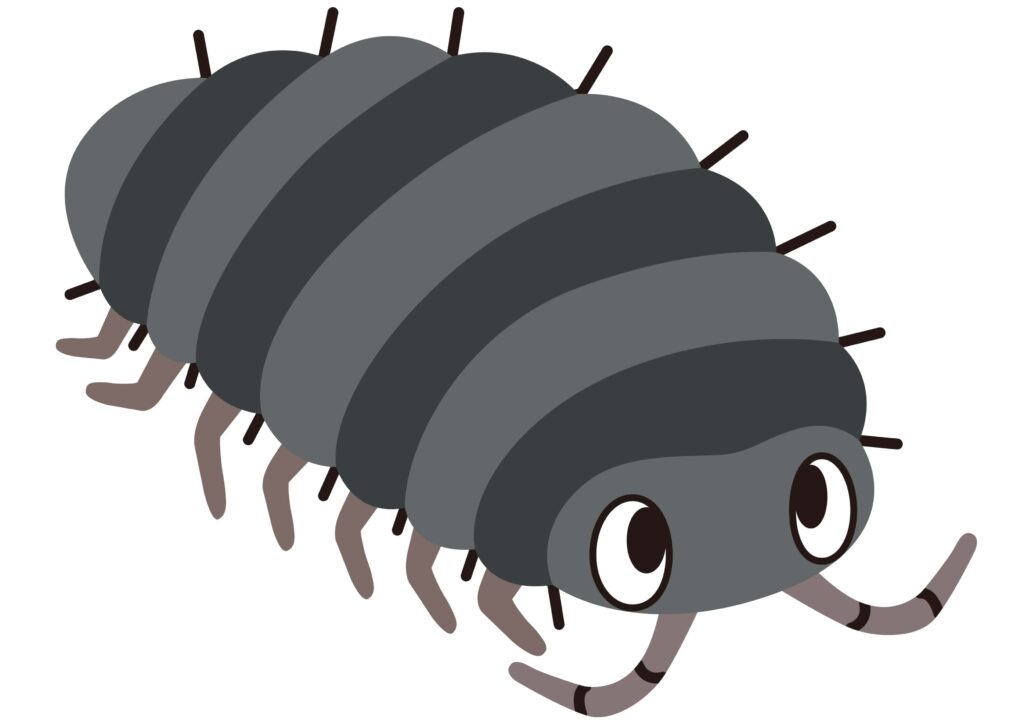
歩くカルシウム、サンショウウオの最強の餌などと言われるワラジムシ。
飼育の容易さも手伝って、カルシウム不足になりやすい我が家のレオパに良いのではないかと期待された。
▼レオパはワラジムシを食べる?生き餌としてのワラジムシについてまとめた記事はこちら
→【歩くカルシウム!】ワラジムシはヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の生き餌として使えるか?
しかし、あまりの需要の低さから、徐々にその意義が失われていったワラジムシ飼育。
管理が疎かになったワラジファームは、あっという間にワラジムシの墓場となった。
しかしミヤコヒキガエルのがまくんとカエルくんの飼育を始めたことにより、再びワラジムシが脚光を浴びることに。
▼ミヤコヒキガエルの飼育についてまとめた記事はこちら
前回のワラジムシ飼育の失敗を糧に、再びワラジムシ飼育始めます。
何故ワラジムシは全滅したか
何故ワラジムシは全滅したか。
原因ははっきりしている。
ずばり管理不足からくる冬場の乾燥による全滅。
程よく湿り気のある状態を好むワラジムシ。
冬場の乾燥には気を配らなければいけない。
▼活き餌を飼育される方はご用心!?
→【両生類・爬虫類は?】蚊取り線香(殺虫剤)がペットに与える影響
ワラジムシの入手
前回のワラジムシの飼育では、ちょっと背伸びをして、オレンジクマワラジムシとやらをわざわざヤフオクで入手。
そう、ワラジムシなんぞ、その辺の適当に採取できるのに。
あわよくば大量に繁殖させて、再びヤフオクへ、などという邪念があったことは否定しない。
今回はシンプルに自分でワラジムシを採取して飼育管理することに。

5分もしないうちにこのくらいのワラジムシが容易に採取できる。
採取した活き餌には何が入っているかわからないとよく言われるが、ニホントカゲやヤモリをみかける環境なので、あまり気にしないことにする。
このワラジムシたちを餌として与えるがまくんとカエルくんも、場所は違えど自然採取されたカエルなのだ。
▼野生のものはちょっと。。。という方はとりあえずまとめて購入して増やすのが良さそう。
ワラジムシ飼育は屋内?屋外?
これまでの経験を踏まえると、ワラジムシ飼育は屋外をオススメする。
▼初めてのワラジムシの飼育繁殖についてまとめた記事はこちら
→ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)のおやつに!】ワラジムシの飼育繁殖に挑戦!!
理由はコナダニ。
前回の飼育では、屋内で飼育していたので、ワラジファームはかなり清潔な状態を意識していた。
餌も1日でなくなる程度を与え、過湿にならないように、2日置きくらいに壁面を中心に霧吹きをして、壁を伝わった水が床材の底面を湿らすように意識していた。
コバエこそ発生しなかったがコナダニは発生した。
ミルワームの飼育でもそうだが、かなり気をつけていてもかなりの乾燥状態を保たないとコナダニは発生する。
ほどほどの湿度が必要なワラジムシの飼育では、コナダニの発生を抑えるのはかなり難しい。
コナダニが発生するとなると、屋内には置いておきたくないのが心情だ。
ちなみにコナダニにはゼオライトが絶大な威力を発揮する。
デュビア飼育などではゼオライトを床材にしてコナダニの発生を抑えられるが、ワラジムシの飼育ではさすがにゼオライトを床材にすることはできない。
コナダニ自体はワラジムシにそれほど悪影響を与えないので、今回は屋外でワラジムシを飼育管理する。
そしてコナダニの発生にはある程度目をつむり、湿り気の管理に全力を注ぐことにした。
ワラジムシの飼育環境
ここからはワラジムシの飼育環境作り。
同じ方法を繰り返してはまた失敗してしまうので床材や飼育ケースなどを少しずつ変えてみた。
準備したものはこちら

- 虫かご(100均)
- 赤玉土(蛙たちの床材と、レオパの産卵床に使用したものの余り。)
- 昆虫マット(ツシマヒラタクワガタの床材のあまり)
- ヤシガラマット
所詮はワラジムシ。
新しいものは購入せず、自宅にあるもので使えそうなものを集めてみた。

まずは虫かごの底に赤玉土2〜3センチ程度敷く。
赤玉土には水分を保持する役目を期待。
赤玉土は乾くと色が変わるので、乾燥の目安にしやすい。
この赤玉土の層が乾いてきているようだと黄色信号だ。

今度は赤玉土の上に昆虫マットを2〜3センチ程度敷く。
この層はワラジムシの餌と床材を兼ねる。
王道ではここは腐葉土が使われることが多そうだが、わざわざ購入したくないのと、腐葉土はコバエが発生しやすいとのことなので、丁度余っていた昆虫マットを使用してみた。
ここで一旦霧吹き。
下の層の赤玉土の色が充分変わる位を目安に湿らす。

さらに昆虫マットの上にヤシガラマットを1〜2センチ程度敷く。
前回はヤシガラマットと水苔を半分ずつ敷いた。
今回は余っている水苔もなく、特別水苔が良かった記憶もないので水苔は使用せず。
このヤシガラマットの層は積極的には湿らせない。
水はけも良く、比較的すぐに乾燥するので、下の層が湿りすぎている時などのワラジムシの逃げ場としては悪くなさそう。

最後に拾ってきた落ち葉を置いて完了。
落ち葉はワラジムシの餌にも隠れ家にもなる、そして何よりもワラジムシを飼育しているという雰囲気がグッと増す。
とりあえずこの環境でワラジムシの飼育繁殖をスタートさせる。
ワラジムシの餌といえばやはり。。。。。
ワラジムシは床材や、落ち葉を食べるので別で餌が必要がどうかは疑問ではある。
ただし間違いなくワラジムシが喜ぶ餌がある。
乾燥アカムシ。
これはワラジムシたちの食いつきがハンパない。

与えるとこのようにすぐにワラワラと寄ってくる。
とにかくこれを与えておけば間違いない。
個人的には、乾燥アカムシの容器には、メダカや金魚、ワラジムシと記載してもらいたいくらいだ。
他には、カルシウム豊富なワラジムシに育ってもらうために、時々カルシウムパウダーもアカムシに混ぜたりしている。
まとめ
今回、ミヤコヒキガエルのがまくんとカエルくんの為に壊滅状態だったワラジムシの飼育繁殖を再開した。
一度失敗してるので、自分なりに改良を加えたつもりだ。
▼ミヤコヒキガエルはワラジムシが大好き?
→ミヤコヒキガエルが餌を食べてくれない。おすすめの餌と餌付けに成功した方法を紹介!!
あまり気持ちのいいものでもないが、数ヶ月後位に、ワラジムシがウジャウジャしている状態になってくれていたら嬉しい。
気づいたことなどあったらまた追記していきたいと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません