レオパ飼育より難しい!?餌用コオロギの飼育管理がうまくいかない

最近、コオロギ飼育の壁にぶち当たっているような気がします。
難しいです、コオロギの飼育。。。。
正直レオパより繊細で難しい。
もうコオロギは嫌だ。。。。。
率直な感想です😩
爬虫類を飼育する者にとっては避けては通れない活き餌の管理。
我が家の餌用コオロギ飼育について反省も兼ねて整理したいと思います。
ヨーロッパイエコオロギは飼いやすい?
飼育しているのはヨーロッパイエコオロギ、通称イエコ。ペットショップでssサイズを100〜150匹程度購入して飼育しています。
大体600〜700円程度で手に入ります。
フタホシと呼ばれるフタホシコオロギではなく、なぜヨーロッパイエコオロギなのか?
まずはそのサイズ。
フタホシは最大で4センチ近くになり、イエコは精々3センチ程度。
ニホントカゲの餌としては3センチ程度がギリギリです。
実際にイエコを与えてる感じとしては、ニホントカゲには1.5〜2センチ程度が丁度良さそうです。
そして、イエコはフタホシより丈夫らしいです。
フタホシは飼育したことがないのでなんとも言えませんが、イエコよりデリケートで死にやすいとよく言われています。
この辺りが、フタホシコオロギよりヨーロッパイエコオロギの方が飼いやすいと言われる理由でしょうか?
後は見た目ですね。フタホシは黒くてサイズも大きめ。
見て目的にちょっとアレなんです。。。。
見る人によってはジャンプするゴキ○リ。
家族的にNGだったので、淡い色のイエコでごまかしている感じです。
結構この理由でイエコを選んでいる人は多いのではないでしょうか?
コオロギの飼育環境
幅30センチ、高さ15センチ程度の虫かごに、卵の紙パック、給水器を設置し、ペットボトルの蓋に亀の餌を砕いて入れています。
まあよくあるコオロギの飼育環境だと思います。
時々昆虫ゼリーも与えてます。
通気性確保のため虫かごの蓋は使用せず、100円ショップで購入できるプラスチック製の鉢底網をクリップでとめて蓋代わりにしています。
卵の紙パックを調達できない時はトイレットペーパーの芯を適当に真ん中で切って、いくつか放り込んでいた時期もありましたが、特に問題はなかったです。
ssサイズくらいだと網目は通過できそうですが、虫かごの高さがそこそこあることと、こちらが手を入れて追いかけ回さなければほとんどジャンプはしないので蓋から脱走されたことはありません。
また、少し成長すると網目は通過できなくなります。
繁殖が目的ではないので、産卵床のようなものは設置していません。
餌は毎日チェックし、少なくなっていれば足します。給水器の水は1週間に1度、掃除の際に取り替えます。
水切れにはもっぱら弱いので、水切れには細心の注意を払います。
掃除をサボると糞尿によるアンモニアが充満し、コオロギも死にやすい環境となります。
虫かごはベランダに置いてます。
ベランダ以外置く場所ありません。。。。
家族がいたりすると室内でのコオロギ管理は難しいものがあります。
日除けなどで陽が当たらないようにはしていますが、大雨でベランダにも雨が降り注ぎそうな時に限り一時的に玄関内に避難させます。
冬場はまだ迎えたことはないのですが、気温が低くなってきたら発泡スチロールに入れて外気から虫かごを保護するつもりです。
ベランダなので電源は取りづらいので、本格的に寒くなったらカイロや湯たんぽで保温しようかと思います。
思えばめちゃくちゃ気を使ってますね、コオロギに。
まあ、冬場はレオパの食欲も落ちるので、そこまで頑張ってコオロギを飼育する必要もないかもしれません。
突然起こるコオロギの大量死
ssサイズで購入したイエコは、5月、6月くらいの気温であれば毎日結構な量の餌を食べ、1ヶ月くらいでぐんぐん成長します。
Lサイズくらいまで成長し、羽化間近な個体も出るくらいで、死んでしまう個体はほぼいません。
順調に管理できているなと思っていると、だいたい2ヶ月近く経つタイミングで毎日バタバタと死んでいきます。
寿命なのでしょうか?
イエコの寿命を調べてみると、成虫になってから2ヶ月〜4ヶ月のようです。
成虫にならずに死んでしまう個体も多く見られるため、寿命ではなさそうです。
原因を色々と探っていますがよくわかりません。
なぜ起こる、謎の大量死😥
空間不足?それともベランダでの飼育が良くないのか。。。コオロギ専用の餌の方がいいのか。。。
空間不足に関しては可能性は否めませんが、ssサイズから死なずに順調に成長したことを考えると飼育場所や餌が悪いと思えません。
空間不足についても、コオロギは成長して大きくなりますが、毎日餌として与えてるため数は減っていきます。
したがって過密という程の状況にはなっていないと思うのですが、この辺ははっきりしません。
もし過密が原因だとすると、それなりの数の餌用コオロギを管理するのは我が家では難しくなってきます。
これ以上大きなケージだとベランダに置くことも難しくなってきます。
この謎の大量死。コオロギを飼育すると割とよくあることのようです。
コオロギ固有のウイルス説も浮上してきます。
怖すぎますね😱
ウイルスだとすると、当面は完全にリセットすることは難しいので、コオロギではない別の種類の餌を検討する必要がありそうです。
イエコはフタホシコオロギより丈夫とはいわれているものの、コオロギはすぐに死ぬとか、雑魚いなどどいわれているのもわかる気がします。
レッドローチはどうなのか
コオロギが厳しいとなるとどうするか。
結局は活餌を必要とする爬虫類飼育者の皆様はここに行き着くことが多いように感じます。
そうです、ゴキ○リの飼育です。
活餌となるゴキ○リのメジャー所はデュビアとレッドローチですが、ニホントカゲやレオパにはデュビアは少し大きいのでレッドローチが候補に上がります。
過密を好む、水切れ餌切れにも驚きの耐久性、栄養価良し、嗜好性良し、ジャンプしない、そして鳴かない。
臭いはコオロギと互角👃
書き忘れていましたが、コオロギは大人サイズになるとめちゃくちゃ鳴きます。
イエコの鳴き声の方が静かなどと言われていますが、うるさいです。
何せ数10匹単位で鳴きますから。
そしてレッドローチはコオロギと比較して成長が緩慢といわれています。
繁殖を目的としていない私にしてみればゆっくりと成長してくれた方がありがたいです。
ちなみに、イエコは、ssサイズを買ってきても、7月8月くらいの気候であれば一月半くらいで鳴くくらいまで成長してしまいます。
レッドローチ。。。ゴキ○リですが、調べれば調べる程、活餌としての無敵っぷりを感じます。
ゴキブリでなければ完全に活餌会のエースとなり得る存在です。
いやぁぁ。。。。。でも、見た目がゴキブリ感満載なんですよね。。。。。。
動きも早いですし。
そもそも餌の時に捕まえられるのだろうか。。。。。
まとめ
ここまでの流れで察している方もいると思います。
私はゴキ○リを飼いたい。
ゴキ○リという名前を除いて、コオロギの勝てる要素が見当たりません。
後は家族を説得できるか。。。息子が幼稚園でよく先生にお話しているそうです。
『父ちゃん、コオロギ一杯飼ってるんだよ!』
なんとなくセーフな感じがします。
コオロギのところがゴキ○リに変わったとすると。。。完全にアウトですね。
無事家族を説得し、レッドローチに切り替えることができましたらまた報告します。
レッドローチではなくまさかのデュビア飼育!!
👇👇👇

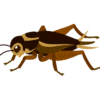

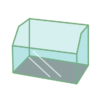











ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません