ワラジムシを飼育繁殖してヒョウモントカゲモドキ(レオパ)のおやつにしたい!

サンショウウオを飼育する人たちからは最強の餌との呼び声の高いワラジムシ。
虫じゃないけどワラジムシ。
エビやカニなどの甲殻類の仲間でカルシウムが豊富🦀🦐
それゆえに、歩くカルシウムなどと呼ばれることもあります。
そんなワラジムシですが、ペットショップなどで購入しようとすると結構なお値段です🤑
もしかして高級餌虫?
以前の記事でも紹介したように、ワラジムシはレオパの主食にするには物足りないですが、何かと使えそうですし、コオロギなどと比較すると管理も楽です。
両生類を飼育している方ならストックしておいて損はないハズ!!
今回はワラジムシの飼育繁殖に挑戦してみたので紹介させていただきます。
ワラジムシをヤフオクで入手
まずはまとまった数のワラジムシを準備する必要があります。
ワラジムシをどこで入手するか。1番簡単なのはその辺に生息する野良ワラジムシを捕獲してくれば簡単に入手できます。
しかもタダです🤩。
しかし今回気になっていたワラジムシはオレンジホソワラジムシという種類のワラジムシ。
その名の通りオレンジ色の体色で、大きさも1cm前後。オレンジ色なのでなんとなく視認性も良さそうで食いつきがよさそう。
さすがにオレンジホソワラジムシは野外で採取するのは難しいのでヤフオク出品されているものを30匹購入しました。
お値段は、送料込みで800円程度。
このまま餌として与えると相当コスパ悪いです😥。
ヤフオクには他にも様々な種類のワラジムシが出品されていて、餌としてではなく、ペットとして購入される方もいるようです。
中々ディープな世界ですね💦
ワラジムシの飼育環境
ワラジムシの飼育環境を整えていきます。
あまり細かな管理は必要なさそうです。
25℃前後を好むようですが、極端に寒くならなければ、活動が鈍くなるだけで、死んでしまうということはなさそうです。
乾燥には弱いので、適度な湿り気には注意します。
また、今回は室内で管理する予定なので、コバエの発生には細心の注意をはかります。
飼育容器
幅20cm、奥行き10cm、高さ10cm程度のタッパーと不織布を100均で購入。
あまり大きな容器は必要としません。
やや過密気味で管理した方が良く繁殖してくれるようです。
タッパーの蓋をカッターなどでくり抜き、くり抜いた部分にグルーガンで不織布を貼り付けます。
網ではなくて、不織布を使用することで、空気を取り入れつつコバエの侵入を防ぎます。
通気は必要ですが、通気性が良すぎると、冬場はあっという間に乾燥してしまいますので注意が必要です。
これで飼育容器は完成。
グルーガンは本当に便利ですね。
虫の飼育にはもはや必須ツールです。
ワラジムシ飼育の床材
ワラジムシの床材といえば腐葉土というくらい腐葉土が定番。
しかし今回は腐葉土は使いません。
なぜならコバエが湧きやすいから。
どんだけコバエに気を使ってんだ!正直自分でもそう思います。
しかし今回は室内管理予定なので、コバエの発生はこのプロジェクトの終了を意味します🙅♂️
代わりに使用するのはヤシガラマットと水苔。
容器の3分の2位にヤシガラマットを5〜6センチ位の高さに敷き詰め、残り3分の1位に湿らせた水苔を敷きます。
ワラジムシは湿った場所で水分を吸収するだけで、常に湿った場所を好むわけではありません。
床材全体を湿らせるような環境にはせず、水分補給のための湿らせた水苔部分と、乾燥した部分をヤシガラマットで作ってあげます。

ヤシガラマットはヤシガラが餌にもなり、隠れ家にもなるのでワラジムシの床材として問題なく使用できます。
コバエなどが気にならないという場合は、乾燥しにくいという利点からも、腐葉土が床材として適している思います。
ワラジムシ自身が分解者なので、掃除は勿論不要です。
床材が減ってくるようなら追加します。
ワラジムシに乾燥は厳禁
前述した通り、ワラジムシは水分を吸収することで水分摂取するので、完全に乾燥させてしまうと全滅してしまいます。
床材使用している水苔の状態を数日ごとにチェックして、常に水苔部分が湿っている状態にしておくことが必要です🌧️
ワラジムシは何を食べる?
ワラジムシは基本何でも食べます。
落ち葉や、野菜くずなどの植物質のものから、亀や魚用の配合飼料などもよく食べます。
床材を入れておけば基本餌切れはしません。
そんな中で断トツでおすすめなのは、乾燥赤虫。
これ、ワラジムシの餌としては唯一無二の存在です。
金魚やメダカの餌として販売されている乾燥赤虫ですが、どういったわけか他の餌と比較すると抜群の嗜好性です。
乾燥赤虫を与えておけば間違い有りません。
ただし注意が必要なのが、乾燥赤虫は動物性の餌。
長期間の留置はダニの発生を意味します。
最初は少量で様子を見て、2,3日で食べ切れる量を与える事をオススメします。
まとめ
春が近いとはいえまだ気温も低い中、何となく簡単そうだから始めたワラジムシ飼育。
室内とはいえ、特にヒーターなどは使用していないため、15℃前後までは温度は下がりますが、乾燥にだけ注意していれば問題なく飼育できています。
飼育容器、床材を用意できればほぼノーメンテナンスで飼育できます。
ただし乾燥には要注意です。
繁殖も、ゆっくりですが、少しずつ増えてきていて、そこそこの数の赤ちゃん子ワラジムシが観察できます。
これから適正気温に近づく春から夏にかけて爆発的に繁殖してくれることを期待してます。
興味のある方(いるのか!?)、是非参考にしてみて下さい。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
※追記
同環境で半年程飼育を続けてみたところ、全滅こそしないものの、ある一定数からワラジムシが増殖しなくなりましました。
餌が悪いのか、環境が悪いのか。。。
検証が必要そうです。
※追追記
その後少し管理を怠けたために冬場の乾燥にやられ、全滅させてしまいました😣
飼育が簡単だと強調しておきながらお恥ずかしい限りです😳
少し環境を見直してまたリベンジしたいと思います。
▼リベンジ!?再びワラジムシの飼育繁殖に挑戦!!



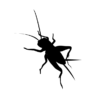









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません